AIとローコードで一気通貫、Kuailu Cloudが描く現実解
業務のデジタル化は「選択」から「前提」へ。
Kuailu Cloudが発表したのは、AIとローコードを組み合わせた企業向けアプリの中核ラインアップです。
現場のスピード感とガバナンスを両立し、コスト/効率/適合性の課題を正面から処理する狙いが見えます。
特に、ヒト・モノ・カネ・運営にまたがるコア領域を共通データ基盤で動かす設計が肝です。
ローコードにより作成・改修のサイクルを短縮し、AIで入力・照合作業を自動化。
“すぐ使えて、すぐ直せる”体験を業務の隅々に届けます。
Kuailu Cloud has launched its Four Core Applications—Human Resources, Procurement, Administration, and Finance.
出典: Laotian Times (2025/09/19)
何が出た?4大アプリの骨子
全体像
今回明示されたのは人事・調達・総務・財務の4領域です。
いずれも企業の日々のオペレーションを支える芯の部分。
紙・Excel・メール依存を減らし、承認・記録・支払いまでを一気通貫でカバーします。
アプリの要点
- Human Resources:人事台帳、異動・入退社、休暇申請、評価のワークフローを標準化。権限やポリシーを跨いだデータ整合も容易に。
- Procurement:申請から承認、発注、検収、請求照合、支払いまでを自動化。リードタイム短縮と入力ミス低減を両立。
- Administration:備品・会議室・社内通達など、散らばりがちな総務タスクを一枚の業務ポータルで統合。通知と共有を標準化。
- Finance:伝票起票、請求/支払管理、予算統制を中心に、請求書OCRや自動仕訳で経理の定型を削減。可視化と内部統制の強化も視野に。
Laotian Timesの報道では、調達は「エンドツーエンドの自動化」、財務は「OCRと自動仕訳によるインテリジェント化」が強調されています。
“標準テンプレート+ローコード拡張”の方針が明確です。
参考: Laotian Times (2025/09/19)
実務にどう効く?ユースケースと使い方
人事・総務の例
入社オンボーディングを例にすると、申請フォームを起点にアカウント付与、備品手配、初日案内までのフローをひとつの画面で完結。
AIが入力の抜け漏れや文面の粗を指摘し、承認者はモバイルで即応できます。
社内告知では、テンプレートを選んで必要事項を埋めるだけ。
言い回しの提案や対象者の自動推薦、既読追跡までが標準機能として利用可能です。
調達・財務の例
調達は、依頼→見積→発注→検収→請求→支払いの全体をローコードのステップで可視化。
異常検知ルールをAIが提案し、リスクが高い取引のみ人手で精査できます。
財務は、請求書OCRで仕訳候補を生成し、規程に反する伝票だけアラート。
決算前の支出サマリや予算乖離をダッシュボードで即時把握し、是正のアクションに繋げます。
AI×ローコード基盤の中核機能
LLM+ローコードの融合
Kuailu Cloudは独自LLMとローコードツールを組み合わせ、業務アプリを“会話的”に構築・運用できるのが強みです。
プロンプトでフォームやフローを生成し、必要に応じてGUIで微調整。
実装のハードルを下げつつ、現場主導の改善を回しやすくします。
Its flagship product, Kuailu Cloud, combines proprietary large language model capabilities with low-code development tools.
出典: Laotian Times (2025/09/24)
テンプレートとマーケットプレイス
CRM、倉庫管理、車両追跡、ワークオーダーなど約30種のテンプレートが用意され、初期導入を短縮。
標準で使い、差分だけローコードで足す発想が合う製品です。
参考: Laotian Times (2025/09/24)
「iInfo」は何者か—名称の位置づけと今後
今回の国内報道や二次情報では「iInfo」という名称の言及があります。
ただし、一次情報として公開されたリリース文で明示されたのはHR/調達/総務/財務の4アプリです。
名称の整合については、地域・媒体での呼称差やテンプレート群の一名称など複数の可能性があります。
編集部見解としては、社内情報ポータル/お知らせ集約の文脈で“iInfo”がテンプレート名として展開される、あるいは総務アプリ配下のモジュール名として扱われる余地が高いと見ます。
一方で、正式な位置づけは今後の追加発表を待つのが賢明です。
導入検討時は、命名=SKUか命名=機能バンドルかを営業窓口で確認するとよいでしょう。
連携とガバナンス—現場が安心して回せる条件
既存システム接続
人事/財務の基幹は企業ごとに様々です。
SaaSやオンプレのAPI、SFTP、Webhook、RPAなど多様な接続方式が必要になります。
ローコードのコネクタとイベント駆動の設計が、二重入力の解消に効きます。
SSO、ロール/属性ベースの権限、オブジェクト/フィールド単位のアクセス制御を標準で備えることも重要です。
監査ログ、承認経路のバージョン管理、データマスキングといった実務の“現実”に耐える機能が、全社展開の可否を分けます。
データ保全とAIの使い方
AI活用では、社外送信の最小化、匿名化、保管域の選択、プロンプト/出力の記録がポイント。
社外LLMを併用する場合は境界の明示とフィルタリングを行い、生成結果の検証ルールを運用に組み込みましょう。
競合比較と導入の考え方
相対評価の視点
- Microsoft Power Platform:M365/Dataverse連携の強さ。既存ライセンス活用でTCOが下がる一方、運用ガバナンス設計が鍵。
- Google AppSheet/Vertex連携:表計算文化との親和性。データ規模が増えると設計の作法が問われる。
- ServiceNow/Flow:ITSM由来の強力なワークフローとCMDB。ライセンス設計は丁寧に。
- Salesforce Platform:CRM起点の拡張性とエコシステム。業務汎用化には設計の一工夫が必要。
Kuailu Cloudの持ち味は、業務オペレーションの“標準テンプレート”が最初から要所を押さえている点にあります。
最初の1マイルが短いので、PoCから本番移行までの道筋を描きやすい印象です。
導入ステップの勘所
- スコープの最小化:申請1種+承認+台帳1つから始め、成果を可視化。
- データ定義の先出し:項目・コード体系・権限境界を最初に合わせると後戻りが減る。
- ロールアウト設計:管理部門→一部門→全社の順でサクセス体験を積む。
- 運用担当の育成:ローコードで直せる人を現場に置く。ベンダー任せにしない。
まとめ—“すぐ使える標準”と“すぐ直せる拡張”の両立
Kuailu Cloudの4大アプリは、企業の根幹業務を標準テンプレートで素早く立ち上げ、ローコードで現場適合を進める現実解です。
AIの自動化とチェック機能が下支えし、入力・照合・承認のムダを削ります。
名称“iInfo”の位置づけには現時点で解釈の幅があるものの、テンプレートやモジュールの拡充が続くなら、情報ポータルと業務フローの融合はさらに加速するでしょう。
まずは小さく始め、成果を可視化しながら、共通基盤に業務を乗せていく。
AI×ローコードの王道アプローチが、いよいよ実装フェーズに入ってきました。
参考リンク:








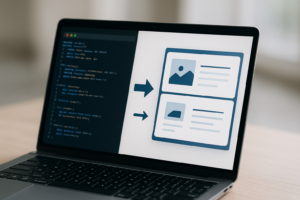
コメント