“見える化”で加速する、現場の生成AI
生成AIは導入して終わりではありません。日々の業務でどれだけ使われ、どれだけ時間が削減できているかを把握できなければ、改善も投資判断も進みません。
HEROZ ASKの活用度ダッシュボードは、この課題に正面から応えます。部署やチームごとの利用実態と時間削減効果を一枚の画面に集約し、次のアクションを導きます。
まずは無償版で提供が始まりました。現場の“今”をとらえ、社内展開を後押しするための最初の一歩です。
有償版では期間指定やCSV出力など、より深い分析まで見据えた拡張が予定されています。
「部署やチーム単位での活用状況や業務削減時間を把握でき、生成AIの利活用を戦略的に推進することが可能となります。」
出典:PR TIMES|HEROZ ASK ダッシュボード発表
「活用状況の見える化で生成AIの戦略的推進を支援。今回の実装は無償版で、有償版は今後実装予定。」
出典:HEROZ株式会社 公式リリース
活用度ダッシュボードの全体像
ダッシュボードは、管理者が組織全体を俯瞰できるように設計されています。
誰が、どこで、どの業務に、どれだけ活用しているかを、過不足なく可視化します。
見えるデータの主なカテゴリ
- 部署・チーム別の利用件数:アクティブユーザー数、プロンプト実行回数、セッション時間など
- 時間削減効果:ユースケース別の推定削減時間、累積時間、1人あたりの平均削減
- ユースケース分布:検索・要約・翻訳・ドキュメント生成などの比率
- トレンド:週次・月次の利用推移、導入前後比較、部門間比較
これらは経営指標と結びつけやすく、導入効果の説明責任を果たすための根拠になります。
活用が進んでいる部署と伸びしろのある部署を同時に把握できる点も、意思決定を速めます。
管理者視点での価値—“使い方の質”までわかる
単なる利用回数の羅列では、現場の改善にはつながりません。重要なのは削減時間と業務タイプの組み合わせで、どこにテコ入れすべきかを特定することです。
見逃したくない示唆
- 高頻度・低削減:頻繁に使われているが効果が薄い。プロンプト改善やナレッジ整備で伸びる余地
- 低頻度・高削減:使えば大きいが使われていない。教育や業務フローへの埋め込みが鍵
- 部署間ギャップ:同一業務でも部門により効果差。ベストプラクティスの横展開候補
こうした示唆は、研修計画やアシスタント設計の優先順位付けに直結します。
可視化は、生成AIを“個人の工夫”から“組織の仕組み”へと引き上げる起点になります。
はじめ方と実務の使い方
導入はシンプルです。管理者がHEROZ ASKにログインし、サイドメニューからダッシュボードを開きます。
初期表示は組織全体のサマリー。ここから部門やチームをドリルダウンします。
基本のステップ
- 1. フィルター設定:部署・チーム、ユースケース、期間を選択
- 2. 指標を確認:アクティブ率、実行回数、削減時間、トップユースケース
- 3. 深掘り:伸びている部署のプロンプト例、活用が薄い部署の阻害要因を特定
- 4. 施策に反映:テンプレート配布、ナレッジの整理、トレーニングの設計
特にユースケース別の時間削減は研修テーマの選定に有効です。
検索・要約に偏っている場合は、ドキュメント生成や翻訳のテンプレートを足すと効果が広がります。
経営に効くKPI設計—“成果”を語る指標づくり
ダッシュボードの数値を経営の言葉へ翻訳することが、推進の成否を分けます。
おすすめは入力指標と成果指標の二軸での管理です。
KPIの例
- 入力指標:アクティブ率、1人あたり実行回数、テンプレート利用率、プロンプト再利用率
- 成果指標:1人あたり月間削減時間、ユースケース別削減時間、案件リードタイム短縮率
- 品質指標:手戻り率、レビュー所要時間、回答の根拠提示率
これらを四半期で振り返り、部門長会議の共通言語にします。
“時間”を“費用”や“機会”に換算できると、投資判断は格段に進みます。
無償版と有償版の違い—まずはスモールスタート
今回のダッシュボードは無償版から利用が始まります。組織の利用状況や時間削減の概況を素早く把握でき、社内共有の土台づくりに向きます。
分析の深堀りや定期レポート化を考えるなら有償版が候補です。
提供範囲の目安
- 無償版:基本的な活用状況の可視化、部署・チーム別の概況、主要ユースケースの分布
- 有償版:期間指定、高度なフィルタリング、CSV出力、より精緻な分析機能の拡張
まずは無償版で“現状の見取り図”を作り、有償版で“意思決定のための分析”に進める流れが現実的です。
詳細は公式の発表と製品サイトをご確認ください。
PR TIMES|ダッシュボード発表 / HEROZ公式リリース / HEROZ ASK 公式サイト
導入のベストプラクティス—データが行動を生む設計
可視化は手段です。組織が動く仕掛けまで設計してこそ効果が定着します。
次のアプローチが実践で効きます。
- 部門別スコアカード:活用度と削減時間を月次で見える化。目標値と差分を明確化
- プロンプトとテンプレの標準化:効果の高い型を共有。再利用率をKPI化
- ベストプラクティスの横展開:伸びている部署の手順を動画や手順書に落とし込み、他部門で試行
- 小さな成功の刻印:週次で“削減時間のハイライト”を知らせ、行動の強化学習を起こす
一方で留意点もあります。
“回数”だけを追うと形骸化しがちです。効果のあるユースケースを増やす視点を忘れないことが大切です。
まとめ—“使われるAI”への近道
HEROZ ASKの活用度ダッシュボードは、生成AIの価値を定量で語るための強力な土台です。部署別の活用と時間削減を同時に捉えることで、投資判断と現場改善が一本化します。
無償版で現状把握を素早く進め、有償版で期間指定やCSV出力を使った深い分析へ。小さく始めて速く回す姿勢が、定着の最短ルートです。
次の一手はシンプルです。ダッシュボードを開き、伸びている部署の型を言語化し、横展開する。
“見える化”が、現場の行動を変え、成果を積み上げていきます。








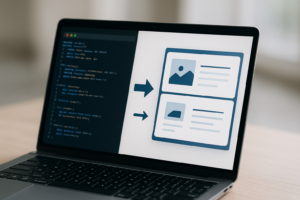
コメント