Claudeがやって来た、その意味
Microsoft 365 Copilotに、AnthropicのClaudeが正式に入ってきました。
これで日々のドキュメント作成やリサーチでも、OpenAI一択ではなく目的に応じてモデルを切り替えられます。
特に長手の推論や構造化された要約が多いチームにはうれしいニュースです。
対象はまず、推論特化のResearcherエージェントと、エージェントを構築するCopilot Studio。
選べるモデルはClaude Opus 4.1とClaude Sonnet 4の2つです。
管理者による有効化とFrontier Programへの参加が前提で、モデル実行はAnthropic側でホストされます。
詳細は公式発表と技術ドキュメントにも明記されています。
参考: Microsoft 365 Blog / Anthropic News / Microsoft Learn / Impress Watch
何が変わる?— マルチモデルの実戦投入
最大の変化は選択肢が増えたことです。
CopilotはこれまでOpenAIの最新モデルが中心でしたが、今回の更新でAnthropicのClaudeをタスク単位で選べます。
Researcherでは「Try Claude」切り替えでOpus 4.1を起動、Copilot StudioではドロップダウンからSonnet 4やOpus 4.1を選択できます。
Microsoftは公式ブログで次のように述べています。
Copilot will continue to be powered by OpenAI’s latest models, and now our customers will have the flexibility to use Anthropic models too—starting in Researcher or when building agents in Microsoft Copilot Studio.
また、Copilot Studioのマルチエージェント機能では、Anthropic・OpenAI・Azure Model Catalogのモデルをタスクごとに組み合わせる設計も可能です。
用途に応じた最適化が社内で完結しやすくなります。
導入の前提— 管理者設定とFrontier Program
最初に必要なこと
Claudeを使うには、組織の管理者がMicrosoft 365管理センターでAnthropicモデルを有効化する必要があります。
ロールアウトはFrontier Program経由で、オプトインしたMicrosoft 365 Copilotライセンス保有組織から順次提供されます。
Microsoft Learnの手順は明快です。
Go to the Microsoft 365 admin center and select Copilot -> Settings. On the Data access page, select AI providers for other large language models. Under LLM providers for your organization, choose Anthropic.
併せて押さえておきたいのは、AnthropicモデルはMicrosoft管理外の環境でホストされる点です。
規約やデータ流通の観点で、社内ポリシーと整合を取りましょう。
データとコンプライアンス— どこで動き、何に同意するか
Anthropicは次のように説明しています。
Anthropic models are hosted outside Microsoft-managed environments and subject to Anthropic’s Terms and Conditions.
つまり、推論はAnthropic側インフラ上で行われます。
従って、取扱データの種類や保存ポリシー、ログの扱い、データ越境の要否について、導入前に法務・セキュリティと合意形成が必要です。
- データ分類: PII/機密/公開の区分と持ち込み可否を明確化
- 規約同意: Anthropicの利用規約・DPAの確認と社内規程への反映
- 監査証跡: プロンプト/応答のロギング方針と保持期限
- 例外運用: 高秘匿案件は既定モデルにフォールバックする運用ルール
この整備ができていれば、マルチモデルの恩恵を安全に享受できます。
Researcherでの体験— 長手の推論に強い相棒
「Try Claude」で切り替えるだけ
Researcherはメール、会議録、ドキュメント、業務アプリ、Webを横断して分析・要約する推論エージェントです。
画面右上のTry ClaudeスイッチでClaude Opus 4.1に切り替えると、複雑な調査・仮説検証・比較整理で力を発揮します。
- 市場参入戦略の骨子作成と根拠リンクの付与
- 四半期レポートの要点抽出と可視化の提案
- 競合比較の観点設定とデータ整理の自動化
実務では、一次情報の引用と出典リンクまでまとめたい場面が多いはず。
長文の精度と根拠の追跡性を重視するタスクで、Claudeは選択肢として強力です。
国内報道も同趣旨で伝えています。参考: 窓の杜 / Impress Watch
Copilot Studioの設計— モデルを役割で使い分ける
ドロップダウンでClaudeを選択
Copilot Studioでは、新規エージェントの既定モデルはOpenAI系ですが、編集画面のモデル選択からClaude Sonnet 4やOpus 4.1に切り替え可能です。
マルチエージェント設計では、タスクごとに異なるモデルを割り当てられます。
- オーケストレーション: 指示分解とワークフロー制御を得意なモデルに
- ディープリサーチ: 長手推論はOpus 4.1で再現性を確保
- 要約・整形: Sonnet 4で軽量に仕上げの体裁を最適化
この役割分担は、コスト・レイテンシ・精度のトレードオフを最小化します。
モデル単独の“万能”を目指すより、工程でベストを組み合わせる方が成果が安定します。
どのタスクでClaudeを選ぶべき?— 実務シナリオ集
Claudeの強みを生かす
- 調査報告書の骨子作成: 仮説立案→論点整理→根拠リンク提示まで一気通貫
- 大量ドキュメントの要点抽出: 長文に強く、見出しと箇条書きが破綻しにくい
- 会議録からの決定事項サマリ: 意思決定とアクションの分離が明確
- 比較表の作成: 観点設計と表形式の整合性が安定
一方で、リアルタイム性や生成のスピードが最優先なら既定モデルを使い、仕上げ段でClaudeに切り替える方法も有効です。
Copilot Studioなら、この切り替えをワークフローに組み込めます。
導入チェックリスト— スムーズなロールアウトのために
- ライセンスとFrontier Program: 対象テナントがオプトイン済みか確認
- 管理センター設定: Copilot → Settings → AI providersでAnthropicを有効化
- 規約同意: Anthropicの規約・DPAを法務とレビュー
- データ方針: 高秘匿データの取扱いと例外運用を定義
- パイロット運用: ResearcherとStudioで小さく試し、成果指標で評価
参考手順: Microsoft Learn
引用と出典
Copilot will continue to be powered by OpenAI’s latest models, and now our customers will have the flexibility to use Anthropic models too—starting in Researcher or when building agents in Microsoft Copilot Studio.
Anthropic models are hosted outside Microsoft-managed environments and subject to Anthropic’s Terms and Conditions.
国内報道: Impress Watch / 窓の杜
まとめ— マルチモデル時代の実務最適化
要点はシンプルです。
ResearcherとCopilot Studioで、Claude Opus 4.1とSonnet 4が選べるようになった。
管理者のFrontier Program参加と明示有効化が必要。
モデルはAnthropic側でホストされる。
この3点を押さえれば、あとはユースケースに応じた配分設計だけです。
まずはパイロットで、既存のOpenAIモデルとの比較を定量化してみましょう。
長手の推論や出典付き要約の精度が上がるなら、本番運用の価値は十分。
マルチモデルを“使い分ける力”が、これからのCopilot活用の差になります。








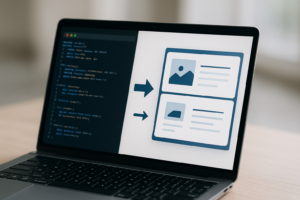
コメント