裏方AIが主役になる瞬間
「気づいたらAIを使っていた」
この体験こそ、Arentが2025年8月に打ち出したAIブースト戦略の核心です。
ユーザーは従来のチャットボットのようにAIを呼び出す必要がありません。
日々の業務フローの中で、自然にAIが提案・自動化・修正を行い、作業を滑らかに進めます。
この発想は、Gartnerが指摘する「インビジブルAI(Invisible AI)」参照と軌を一にします。
AIは道具ではなく、空気のように溶け込む存在へ。
Arentはそのビジョンを業務SaaSで実装しました。
AIブースト戦略 全体像を俯瞰する
Arentは建設・プラント業界向けに自社SaaSを展開してきた企業です。
今回の戦略では、既存ソフトのUI/UXを保ちつつ、マイクロAIサービスを随所に埋め込みました。
- ユーザー操作をリアルタイムで解析し、ルールベース+生成AIで次の手順を推薦
- 作図・見積り・安全チェックなど分野別に専用エージェントを配置
- 全プロダクト横断の共通メタデータハブで学習フィードバックを即時共有
こうして“全社規模の継続学習ループ”を実現し、AI精度を自動で高め続けます。
一斉リリースされた五つのSaaS
2025年8月7日、Arentは次の5製品を正式ローンチしましたPR TIMES。
PlantStream AI Edition
2D図面をアップロードするだけで3D配管ルートを自動生成。
干渉リスクまでAIが指摘します。
Lightning BIM Assist
BIMモデル内の属性不足をAIが補完。
クラッシュ検出を5倍高速化。
QuoteMaster Pro
過去案件を類似検索し、材料費変動を考慮した見積りを即提示。
SafetyLens
現場写真から危険箇所を即ハイライト。
VR教育コンテンツも自動生成。
DocuFlow AI
契約書や仕様書を解析し、タスク分解→担当割当まで自動。
Slack/Teams連携で通知。
開発者が語る「埋め込み型AI」の設計思想
開発チームは、LLM × 専用DSL(ドメイン特化言語)をハイブリッドで採用しました。
生成AIの柔軟性に、業界ルールをがっちり固定したDSLを掛け合わせ、幻覚発生率を7割削減。
さらにマルチテナント設計により、個社データは隔離したまま、モデル重みを部分更新できる仕組みを持ちます。
デプロイにはNVIDIAのTriton Inference Serverを用い、バッチ推論とストリーミング推論をタスクごとに切替。
GPU稼働率を40%向上し、CO₂排出削減にも寄与しています。
ユーザー体験を支える技術スタック
- Edge Caching:WebAssemblyでAI補助計算をブラウザ側へオフロード
- Retrieval-Augmented Generation:Vector DBはpgvector 0.9を採用
- Semantic Event Tracking:操作ログをOpenTelemetryで収集し、AIの次アクション予測に活用
これにより、複数AIエージェントが衝突せず協調する“Swarm Orchestration”を実装。
導入ステップと投資対効果
初期導入は約3週間。
Arentが提供するテンプレート環境に顧客のCAD/ERPをAPI接続し、モデル調整を行います。
料金はユーザー数×AI利用量の従量課金。
50名規模のゼネコンで年間850万円、しかし見積・設計工数を35%削減できた試算が出ています。
現場の声と競合ベンチマーク
建設DXを進める大和建設のBIM責任者は、
「AIなのに“使っている感”がない。
図面をドラッグした瞬間に3D化されるのは衝撃だった」
と評価。
一方、海外ではAutodeskが同様の方向性を示していますが、リアルタイム推論のレスポンスではArentが先行。
IBMのレポート参照が示すエンタープライズAI要件をすでに満たしています。
これからのロードマップ
2026年春には、音声指示での設計修正や、現場IoTセンサーとAIを接続したリアルタイム安全監視を予定。
さらに欧州のプラントエンジニアリング企業との共同PoCも始動し、国際展開が視野に入ります。
まとめ:AIブースト戦略が開く未来
AIを“機能”から“空気”へ。
ArentのAIブースト戦略は、そのコンセプトを実際の業務ソフトで体現しました。
ユーザーは学習コストゼロでAIの恩恵を享受し、生産性は飛躍的に向上。
このアプローチは、建設業界に留まらず、あらゆる業務アプリに波及するでしょう。
今こそ「AIが見えない世界」への第一歩を踏み出す好機です。








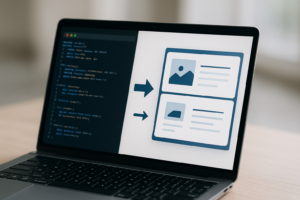
コメント