95%がAIを使う職場へ——加速するGMOのAIシフト
GMOインターネットグループの生成AI業務活用率が95%に到達しました。
複数AIサービスの使い分けも一気に進み、職場の“AI前提”が現実のものになっています。
成果は数字にも表れ、削減できた時間は新たな価値創造に回りはじめました。
キーワードは、複数モデルの併用、現場主導のバイブコーディング、そして仕組み化されたリスキリングと投資です。
本稿では、最新データと現場の使い方を読み解き、他社が再現するための要点まで整理します。
記事のサマリー:複数AIサービス利用率80%、月25.1万時間削減(人手換算約1,572人分)と試算。
数字で読み解くインパクト
四半期ごとに公開される定点調査の最新結果は明快です。
業務活用率95%、複数AIサービス利用率80%、月間25.1万時間の業務削減(約1,572人分)。
利用は習慣化し、精度・速度の両輪で成果が出ています。
- 利用率:生成AIの業務活用率95.0%
- マルチAI:複数AIサービスの利用率80.0%
- 削減効果:月25.1万時間削減(約1,572人相当)
- 有料ツールの積極利用:「AIブースト支援金」効果で有料契約率も高水準
- 開発現場:Gemini CLIやClaude CodeなどのAIコーディングエージェントを用いた「バイブコーディング」経験者が6割超
「生成AIの業務活用率は95.0%に到達。複数AIサービス利用率は80.0%、月間25.1万時間の業務削減に相当」
PR TIMES:GMOインターネットグループ(2025/10/1)
「生成AI導入によるグループ全体の月間削減時間は約25.1万時間。これは1,572人分の労働力に相当」
CreatorZine(調査結果の要約)
複数AIを使い分ける組織設計
GMOが強いのは「最適ツールを最適用途に」という思想の徹底です。
モデルやサービスごとの得意領域を見極め、社内推奨の比較ハブやナレッジ共有で使い分けを日常化しています。
その基盤により、80%という高い複数AI利用が実現しました。
具体策として、複数モデル比較の導線や、ガバナンスとセキュリティのルール化、有料ツールの導入支援が一体で設計されています。
調達と教育が分断されないため、現場は迷わず使い分けに踏み出せます。
- ナレッジ整備:社内ポータルでプロンプト、ワークフロー、成功事例を共有
- 比較・検証:用途別に最適モデルを選べる評価フレーム
- セキュリティ:データ種別ごとに取り扱い・持ち出しの可否を明確化
現場での使い方——非エンジニアも“バイブコーディング”
開発者はもちろん、非エンジニアがAIエージェントと並走する「バイブコーディング」が広がっています。
テキスト生成だけでなく、要約・調査・仕様整理・スクリプト化まで一気通貫で支援します。
小さな自動化の積み重ねが、月間25万時間の削減を生みました。
代表的なユースケース
- 会議効率化:議事録生成、要約、タスク抽出、フォローアップ文面の自動作成
- ドキュメント整備:要件定義の素案、仕様差分の比較、チェックリスト化
- 業務の自動化:RPA×LLMで定型処理を自走、監視・ログ要約を標準化
- 開発の加速:Gemini CLI/Claude Code等で設計レビュー、テスト生成、コード修正提案
ポイントは“一つのモデルで全部やらない”こと。
生成、検証、校正、要約…フェーズごとに強いモデルを切り替えると、品質と速度が両立します。
複数AIの“編成”が、成果の再現性を高めます。
仕組みと文化——「虎の穴」と「AIブースト支援金」
現場を支えるのは、学習の仕組みと投資の継続です。
短期集中の社内リスキリング「虎の穴」で非エンジニアの自動化スキルを底上げ。
さらにGMO AIブースト支援金で有料AIの導入ハードルを下げ、現場の試行錯誤を後押しします。
- 虎の穴:AI・RPAの集中育成で“使いこなす層”を継続的に輩出
- 支援金:有料ツールの契約を推奨し、精度と再現性を確保
- 四半期サイクル:活用実態を定点観測し、施策を迅速にアップデート
「AI人財の支援に年間約10億円を投資。GMO AIブースト支援金を創設」
GMOインターネットグループ 公式リリース
成果を再現する戦術——あなたのチームで試すなら
GMOのやり方は、規模を問わず再現できます。
鍵は“使い分けを前提にした運用”と“教育×調達×ガバナンスの同時立ち上げ”です。
次のチェックリストから着手しましょう。
- 業務棚卸し:要約、下書き、差分比較、QA生成など「AIが得意」な粒度に分解
- モデル方針:生成・要約・校正・評価のフェーズ別に推奨モデルを定義
- プロンプト資産:業務別テンプレと評価手順を社内ポータルで更新
- 導入支援:有料ツールの試験導入と費用負担ルールを明確化
- 品質ゲート:出力の“人間確認”とログ保存・再現検証の仕組みを標準化
特に評価の自動化が効きます。
ベンチマーク用のテストプロンプト・期待出力・採点基準を用意し、モデル更新時に回すだけで劣化や改善を可視化できます。
継続運用のコストが一気に下がります。
リスクとガバナンス——拡大期のつまずきを避ける
利用が広がるほど、情報管理と出力の信頼性が重要になります。
GMOは用途別ルールと教育で、拡大と統制を両立させています。
導入企業も「最初から」ルールを明記しましょう。
- データ区分:顧客・機微・社外公開の区分ごとに投入可否を定義
- モデル選定:社外API利用時は匿名化、社内データは閉域で処理
- ハルシネーション対策:根拠リンク必須、査読者の責任分担を明確化
- 監査可能性:プロンプト・出力・修正履歴のログ化と保管
また、“AIが書いたまま”を出さない文化も重要です。
レビューとA/B比較、計測に慣れるほど、品質は加速度的に上がります。
まとめ——削減から価値創造へ
GMOは95%活用と25.1万時間/月の削減を通過点に、価値創造フェーズへ舵を切りました。
複数AIの使い分けと、学習・投資・ガバナンスの三位一体運用が、現場の“当たり前”を更新しています。
他社が学ぶべきは、編成(オーケストレーション)としてのAI運用と、仕組みの同時立ち上げです。
最小構成で良いので今月から回し、来月には測り、四半期で拡張する。
それが“95%の壁”を越える最短ルートです。
参考:
PR TIMES(GMO:生成AI業務活用率95%) /
CreatorZine(要点まとめ) /
GMO公式:AIブースト支援金








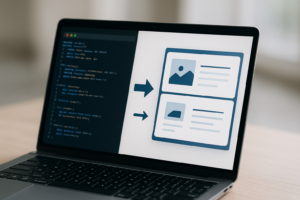
コメント