ターミナルに降りてきた“副操縦士”
GitHubが、Copilotのコーディングエージェントをターミナルへ直送する「Copilot CLI」をパブリックプレビューとして公開しました。
エディタやブラウザに切り替えることなく、手元のコンソールでAIと対話しながら、コード調査や実装、デバッグまで一気通貫で回せます。
対応はCopilot Pro / Pro+ / Business / Enterprise。
macOS・Linuxに対応し、Windowsは実験的サポートとして提供が始まっています。国内報道や開発者ブログでも詳細が相次いでいます。
- 公式発表(Changelog): GitHub Copilot CLI is now in public preview
- 機能概要(英語): github/copilot-cli (GitHub)
- 国内解説: 窓の杜 / Publickey / ソフトアンテナ
Copilot CLIの正体と何が変わるのか
Copilot CLIは、ローカルで同期的に動く“コードとGitHubの文脈を理解するエージェント”です。
リポジトリを横断して仕様や依存を調べ、Issue起点で実装の雛形を用意し、テストやビルド、簡易デバッグまで会話で進められます。
特徴的なのは、MCP(Model Context Protocol)に対応し、既定のGitHub MCPサーバーを通じてIssueやPRなどのクラウド側コンテキストを参照できる点。
手元のコードとリモートの履歴・議論をひと続きの会話に統合できるため、調査から実装、検証までの“分断”が減ります。
- 対象プラン: Copilot Pro / Pro+ / Business / Enterprise
- 対応OS: macOS / Linux(Windowsは実験的)
- 要件: Node.js 22+ / npm 10+(WindowsはPowerShell 6+推奨)
- MCP対応: 既定のGitHub MCPに加え、カスタムMCPサーバーを追加可能
公式リポジトリの説明も示唆的です。
We’re bringing the power of GitHub Copilot coding agent directly to your terminal. With GitHub Copilot CLI, you can work locally and synchronously with an AI agent that understands your code and GitHub context.
セットアップと最初の会話
インストールとログイン
セットアップはシンプルです。Node.jsとnpmを用意し、グローバルにインストールします。
初回起動時はブラウザが開き、GitHubアカウントで認可します。
- インストール:
npm i -g @github/copilot - 起動:
copilot(初回は/loginで認証) - モデル切替:
/modelで利用可能なモデルを選択
プレビュー開始後、モデル選択や許可制御なども強化されました。
最新のChangelogでは、/modelでの切替や、--allow-tool/--deny-toolの強化(glob対応)などが案内されています。
基本フロー
ターミナルでCopilotを起動したら、リポジトリ直下で自然言語の指示を与えます。
「このIssueを実装するための差分を提案して」「テストが落ちる原因を調べて」「このフォルダ構成を説明して」など、会話で進めます。
- リポジトリの要約・依存調査
- Issue/PRの文脈を踏まえた実装支援
- ビルド・テスト・簡易デバッグの段取り提案
- スクリプトやコマンドの説明・修正案
結果は常に“確認と実行”の二段階。
提案の吟味と権限確認を挟める点は、CLIならではの安心感があります。
旧「gh-copilot」からの移行ポイント
GitHub CLI拡張としての「gh-copilot」は非推奨となり、新しいCopilot CLIへ置き換えが進みます。
GitHub Docsでも明記されています。
The GitHub Copilot extension for GitHub CLI has been deprecated. It has been replaced by the new GitHub Copilot CLI.
出典: GitHub Docs
移行は段階的に。組織やエンタープライズ環境では、管理者がポリシーでCLIの利用可否を制御できます。
手元の環境で旧拡張を使っていた場合は、早めの切替をおすすめします。
- 組織設定でCopilot CLIの許可を確認
- 手元では新CLI(copilotコマンド)に一本化
- ワークフローやスクリプトの呼び出し先を更新
国内記事や速報では、10月下旬に旧拡張の廃止が言及されています。
最新のアナウンスはChangelogとDocsを定期的に確認しておくと安全です。
どこまでできる?現場ユースケース
調査と実装の“橋渡し”を一気通貫に
コンテキストを跨いだタスクが得意です。
Issueの要件を読み込み、関連ファイルや過去議論を当たり、実装の叩き台を生成。テストやLintの落ちどころまで会話で導きます。
- 新規コードベースの読解: 構成と責務を要約し、変更箇所の当たりを付ける
- Issue駆動の実装: ラベルや議論を踏まえて差分案を提示
- ローカルデバッグ: 失敗ログの要約と原因候補、再現手順の提案
- ドキュメント生成: READMEやRunbookの初稿生成と差分適用
CLIに常駐することで、IDE/ブラウザ/ターミナルの往復を大幅に削減。
“調べる→書く→確かめる”を会話のリズムにまとめます。
権限・モデル・エンタープライズ対応
プレビュー以降、モデル選択とツール実行の許可制御が強化されています。/modelで利用モデルを即切替でき、--allow-tool/--deny-toolはglobに対応。shell(npm run test:*)のように、許可範囲の粒度を上げられます。
- モデル制御: セッション単位で切替。応答品質や速度のチューニングが容易
- 許可リスト: 破壊的操作や秘匿領域へのアクセスを明示的に遮断
- Enterprise配慮: サブスクリプション単位のAPIエンドポイント準拠など、ネットワーク要件に適合
- 認証: 通常認可に加え、Copilot Requests権限付きのきめ細かいPATも利用可
長い会話でのコンテキスト圧縮に近づくと警告が出るなど、運用上の見通しも向上。
セキュリティとUXの綱引きに現実解を出しつつあります。参考: GitHub Changelog
他ツールとの住み分け
Claude CodeやGemini系のCLIエージェントと比較した強みは、GitHub文脈との一体化です。
Issue/PR/ディスカッションをMCP経由で取り込み、変更提案に直結できる点は現場の実務に刺さります。
- Copilot CLI: GitHub文脈の一次市民。リポジトリ中心の変更サイクルに強い
- 他エージェント: 外部検索や多言語QAは強力。だがリポジトリ統合は工夫が必要
実装~検証はCopilot CLI、要件探索や外部リサーチは別エージェントと併用。
そんな“役割分担”が、最短で成果に届く組み合わせになりそうです。
チーム導入の実務チェックリスト
プレビュー段階でも、十分“現場投入”可能な成熟度です。
ただし、チーム導入ではガバナンスも同時に設計しましょう。
- ポリシー: 組織設定でCopilot CLI許可。機密領域の扱いを明文化
- 権限:
--allow-tool/--deny-toolのプリセットを役割別に用意 - モデル: 目的別に推奨モデルを定義(速度/精度/コストのバランス)
- 監査: 変更提案→レビュー→適用のゲートを自動化
- ナレッジ: 実例プロンプトをレシピ化。成功/失敗事例をリポジトリに集約
なお、旧gh-copilot拡張は非推奨・廃止予定です。
CLI体験を標準化するなら、切替は早いほど学習コストが低く済みます。参考: GitHub Docs
まとめ:CLIが主役になる日
Copilot CLIは、“リポジトリと会話する”開発体験をターミナルに持ち込みました。
調査・実装・検証の往復を会話のモードで連結し、作業の分断を小さくします。
プレビューの今でも、モデル選択と権限制御は実用十分。
エディタ偏重のワークフローに、もう一つの“主役”が加わる感覚です。
- 始めるなら今: 旧拡張は非推奨。移行の学習コストが低いうちに
- まずは小さく: Issue駆動の小タスクから会話で回し、型を作る
- 運用もセットで: 権限・監査・モデル選択のベストプラクティスを整備
ターミナルで、コードの文脈を理解する相棒と対話する。
その素朴な体験が、チームのスループットを静かに底上げしていきます。








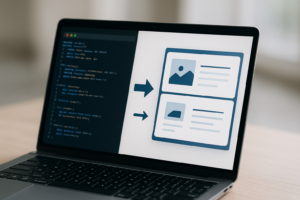
コメント